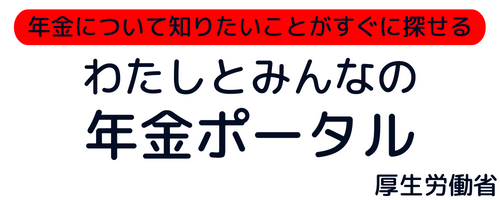【専門家が解説】脳梗塞の後遺症で障害年金は受給する際のポイントとは?

日本人の死因の1位は、がんです。2位が心疾患、3位が脳血管疾患です。この2つは、動脈硬化疾患です。脳血管疾患の主なものが脳梗塞です。
今回は、私たちの身近な病気である脳梗塞で障害年金を申請する際のポイントを解説します。
|
目次 |
脳梗塞とは
脳の病気の多くは、脳の血管が破れたり、詰まったりという障害が起こります。そして脳の機能の一部が壊れてしまうことによって発症します。脳梗塞を含む多くの脳疾患を「脳血管疾患(障害)」と呼びます。
脳梗塞の梗塞とは、「ものが詰まり流れが通じなくなる」という意味です。脳梗塞は、血栓と呼ばれる血のかたまりが血管を塞ぎます。そしてそこから先に血液が流れなくなってしまいます。詰まった先の細胞や組織は、酸素や栄養が送られず、壊死してしまいます。脳は大きなダメージを受けます。脳梗塞は突然発症し、数分から数時間で急速に症状が進みます。
脳梗塞のタイプと発作
| 脳卒中 | 脳梗塞 | ラグナ梗塞 |
| アテローム血栓性脳梗塞 | ||
| 心原性脳塞栓症 | ||
| 脳出血 | ||
| くも膜下出血 | ||
脳卒中は、脳梗塞、脳出血、くも膜下出血に分かれます。脳梗塞は、脳卒中死亡の60%を閉めています。
脳梗塞は、以下の3つに分類されます。
| ラグナ梗塞 | 脳の細い血管に動脈硬化が起こり、詰まってしまう |
| アテローム血栓性脳梗塞 | 脳の太い血管の内側にドロドロのコレステロールの固まりができ、そこに血小板が集まって動脈をふさいでしまう |
| 心原性脳塞栓症 | 心臓にできた血栓が流れてきて血管をふさいでしまう |
脳梗塞の原因
脳梗塞の原因の一番は、動脈硬化です。動脈硬化とは、血管の内側の壁にコレステロールなどがたまり、血管が厚く、堅くなり、血液の流れが悪くなってしまった状態です。
この動脈硬化にさせる病気は、高血圧、脂質異常症、糖尿病、心房細動などがあります。
これらの原因は、喫煙、飲酒、肥満です。脳梗塞などの動脈硬化性疾患は、生活習慣病です。増えた油が少しづつ血管の内側にたまるなどして、進行していきます。
脳梗塞の後遺症で障害年金は受給できます
障害年金は、一定の基準を満たす限り、どのような病気に基づくものでも支給の対象となります。
もちろん、脳梗塞を発送して障害が残った場合にも、障害の状態が障害認定基準をみたすものであれば、障害年金の対象となります。
脳梗塞の患者数は、非常に多いです。当然、その障害にお悩みの方も多くいらっしゃいます。
脳血管障害で障害年金を受給される方も他の障害と比較すると多くなっています。
脳梗塞後遺症の認定基準
脳梗塞の後遺症は、体の様々な場所に発病するため、症状が出ている部位ごとに認定基準が異なります。
障害年金を申請する場合には、障害の状態によって障害年金の申請の際に試用する診断書が異なります。
申請する前の目安としては、以下のとおりです。
1.身体障害についての基準
片麻痺、半身麻痺による場合の基準は以下のとおりです。
| 1級 | ・両腕がまったく動かない状態
・両手のすべての指が全く動かないもの、又は全ての指の機能に著しい障害がある状態 ・両脚が全く動かない状態 |
| 2級 | ・眼を閉じた状態で立ち上がり、自力で立った状態を保てない、または目を開けて直線を歩行中に10メートル以内で転倒、あるいは著しくよろめいて歩行を中断せざるをえない程度の状態
・両手の親指及び人差し指または中指の機能に著しい障害を有する状態 ・左右どちらかの腕がほとんど動かせない状態 ・左右どちらかの腕のすべての指がほとんど動かせない状態 ・左右どちらかの脚がほとんど動かせない状態 |
| 3級
(※初診日に厚生年金加入者だった場合のみ該当) |
・眼を閉じた状態で立ち上がり、自力で立った状態を持続させることが不安定で、目を開けて直線を歩行中に多少転倒しそうになったりよろめいたりするが、どうにか10メートル歩き通す程度の状態
・左右どちらかの腕の3大関節(肩・肘・手首)のうち、2関節以上動かす事が出来ない状態 ・左右どちらかの腕の人差し指、中指、薬指、小指がほとんど動かせない状態 ・左右どちらかの脚の3大関節(股・膝・足首)のうち、2関節以上動かすことができない状態
|
2.そしゃく、えんげ障害についての基準
| 2級 | ・流動食以外は摂取(せっしゅ)できない状態
・経口で食事が摂(と)れない状態 ・経口で食事を摂るのが極めて困難な状態 (食事が口からこぼれ出るため常に手や器物でそれを防がなければならない、1日の大半を食事に費やさなければならないなど) |
| 3級
(※初診日に厚生年金加入者だった場合のみ該当) |
・経口摂取のみでは十分な栄養がとれないためゾンデ栄養(鼻から胃にカテーテルを通して栄養物を流し込むなど)の併用が必要な状態
・全粥または軟菜以外は食べられない状態 |
3.言語障害についての基準
構音障害、音声障害、失語症の基準は以下のとおりです。
| 2級 | ・発音に関わる機能を喪失するか、話すことや聞いて理解することのどちらか又は両方がほとんどできないため、日常会話が誰とも成立しない状態 |
| 3級
(※初診日に厚生年金加入者だった場合のみ該当) |
・話すことや聞いて理解することのどちらか又は両方に多くの制限があるため、日常会話が、互いに推論したり、たずねたり、見当をつけるなどで部分的に成立する状態 |
4.視力・視野についての基準
| 1級 | ・両眼の視力の和が0.04以下 (矯正視力) |
| 2級 | ・両眼の視力の和が0.05以上0.08以下 (矯正視力)
・両眼の視野が5度以内(I/2指標で測定) ・両眼の視野が10度以内(I/4指標で測定)で、かつ中心10度以内の8方向の残存視野のそれぞれの角度の合計が56度以下(I/2指標で測定) |
| 3級
(※初診日に厚生年金加入者だった場合のみ該当) |
両眼の視野が0.1以下に減少した状態 (矯正視力) |
5.聴力についての基準
| 1級 | 両耳の聴力レベルが100デシベル以上 (矯正していない状態で) |
| 2級 | 両耳の聴力レベルが90デシベル以上
両耳の平均純音聴力レベル値が80デシベル以上で、かつ、 最良後音明瞭度が30%以下 (矯正していない状態で) |
| 3級
(※初診日に厚生年金加入者だった場合のみ該当) |
両耳の平均純音聴力レベル値が70デシベル以上
両耳の平均純音聴力レベル値が50デシベル以上で、かつ、 最良後音明瞭度が50パーセント以下 (矯正していない状態で) |
6.記憶・注意・精神障害についての基準
| 1級 | ・高度の認知障害、人格変化、その他の精神神経症状が著しく、常に援助が必要な状態 |
| 2級 | ・認知障害、人格変化、その他の精神神経症状が著しいため、日常生活に大きな制限を受ける状態 |
| 3級
(※初診日に厚生年金加入者だった場合のみ該当) |
・認知障害、人格変化は軽度であるが、その他の精神神経症状があり、労働が制限をうける状態
・認知障害のため、労働に著しい制限を受ける状態 |
書類作成に関する3つのポイント
書類作成に関する3つのポイントについて解説します。
1.特別に、初診日から6ヶ月で申請できる場合がある
本来、障害年金は、初診日から起算して1年6ヶ月経過した時点で申請が可能となります。しかし、脳梗塞を原因とした障害で申請する場合は、これが、6ヶ月に短縮される場合があります。それは、医師がこれ以上リハビリしても治癒しないと判断した場合(症状固定)です。この場合、6ヶ月目から申請可能となります。
6ヶ月が経過したら、医師に症状固定しているかどうか確認しましょう。症状固定していて、日常生活、仕事に支障があるのであれば、すぐに障害年金を申請できます。
2.診断書のポイント
審査結果を左右するのは、診断書です。障害年金が受給できるか、1級、2級、3級の結果を左右します。診断書が最も重要となります。医師に診断書の依頼をする前に、下記の点をぜひ参考にしてください。
①症状に応じた診断書を用いる
脳梗塞がどの場所にでているかによって診断書が異なります。症状に応じた診断書を用いることがポイントです。ケースによっては2種類の診断書を組み合わせることも可能です。
| 症状 | 診断書 |
| 身体の麻痺、しびれの症状 | 肢体の障害用 |
| 聴覚、そしゃく・嚥下といった食べ物を摂ること、言語障害 | 聴覚・鼻腔機能・そしゃく・嚥下・言語機能の障害用 |
| 失語症 | 言語機能の障害用・精神の障害用 |
| 視力、視野などの目に関する症状 | 眼の障害用 |
| 意識障害、いままでできていたことができなくなった等の認知障害 | 精神の障害用 |
②診断書はもれなく書いてもらう
診断書があまりにも多く、記入する蘭がたくさんあります。医師は忙しさにかまけて、すべての項目について記入できていない場合もあります。それは仕方のないことかもしれません。しかし、お役所の審査は、全項目について、ひとつひとつが非常に大きな影響をもたらします。医師から診断書を受け取ったら、できるだけその場で確認し、疑問点があれば、医師等にしっかりと確認しましょう。
③日常生活や就労状況について医師に伝えておく
診察中に医師に、生活や仕事に状況をきちんと話ができていないのではないでしょうか?それではいけません。これは、非常に重要なことです。しっかりと現在の生活や仕事に状況について伝えておきましょう。
診断書のなかには、「日常生活状況や就労状況について」として、医師が客観的にみて記入する蘭があります。これは、必ず書かなければならない項目です。しかし、医師が、実際には、後遺症が働くことができなくなっていた場合でも、「労働可能」と書いてしまうことがあります。
「後遺症で働くことができなくなった」「就労時間に制限を設けなければならなくなった。フルタイム週40時間で働けなくなった」「日常生活として1人で外出できなくなった」「体調不良で半日は寝ていなくてはいけない」などしっかりと医師に伝えておきましょう。
3.病歴就労状況等申立書をしっかり書こう
①診療の内容はしっかり詳細に書きましょう。
診療の内容で、できるだけ詳細にしっかりと記載します。医師から言われている生活するうえでの注意点や仕事をするうえで注意することなどをしっかり書きましょう。
②日常生活で困っていることをしっかり書きましょう。
脳梗塞の後遺症で、日常生活でいかに困っているかをしっかり書きましょう。仕事をするうえで困っていることもしっかり書きましょう。
③診断書との整合性をとることが最も重要です。
診断書との整合性が最も重要です。診断書の中に記載のない症状について、病歴就労状況等申立書に書いても、それは、無視されることとなります。
したがって、診断書の内容と病歴就労状況等申立書の内容を照らし合わせて、しっかりと整合性を取る必要があります。
実際に起こっていることが事実です。ということは、医師が知らないことがあるはずです。それであれば、診断書を記載した医師に相談してみることが必要となります。
脳梗塞で障害年金の申請をお考えの方は当事務所へご相談ください
「自分の場合はどうだろう?」「まずは何から始めればいいのだろう」という疑問が生じた場合は、沖縄障害年金サポートにご相談ください。
料金は、ご相談者が障害年金を受給できた場合のみ発生するかたちになっています。安心して、ご相談ください。
|
まずはお電話か問い合わせフォーム・LINEでご予約ください メールでお問い合わせはこちらから LINE相談はこちらから ※電話受付時間 : 平日9:00~17:00 ※メールは24時間受付中 |
ま











 キーワード検索
キーワード検索

 初めての方へ
初めての方へ